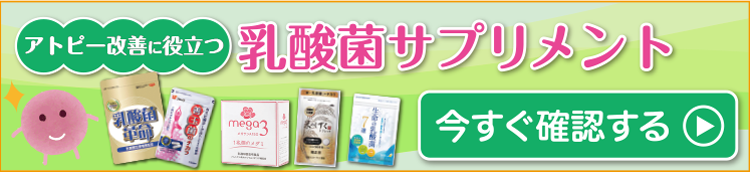アトピーの治療のために病院に行くと、必ずと言っていいほど処方されるのが「ステロイド」です。ステロイドはアトピーの症状を強力に抑えてくれる薬です。しかし、その反面、アトピーそのものよりも重大な副作用をもたらす危険性がある薬でもあり、1970年代後半にはその安易な使用による副作用が問題になったこともあります。
「病院でステロイドを処方されたが、本当に使って大丈夫なのか」と不安に思っている方や、「すでにステロイドを使用しているけれど、このまま使い続けても大丈夫か」と疑念を抱いている人も多いのではないのでしょうか。
私自身、ステロイドを使用していた時期があり、ステロイドの使用を中止してステロイド依存症を治す「脱ステロイド」や、それに伴う症状のぶり返しである「リバウンド」も経験しました。そのため基本的にはステロイドは使用すべき薬ではないという意見を持っており、使わずに済むならそれが1番と考えています。
しかし、中には症状が重すぎたり、社会人であれば社会生活を維持するために強力に症状を抑えなくてはいけなかったりなど、ステロイドを使用せざるを得ない場合もあるように思います。
その場合においても、ただ医師に言われるままにステロイドを使用してはいけません。
アトピーを治すのは誰(何)でしょうか。それは「自分」です。医師はそのためのアドバイザーであり、ステロイドはそのための「道具のひとつ」に過ぎません。
ステロイドを使用するならば、使用者であるあなたも、ステロイドについてしっかりと学ぶ必要があります。そうでなければ、ステロイドによる治療を選択した場合もそうでない場合も、不安が残り治療に専念できないでしょう。
このページではステロイドの良し悪しや副作用について言及するのではなく、「ステロイド薬」とは何なのかを紹介していきます。
目次|このページでわかること
そもそも「ステロイド」とは何者なのか?
まず、「ステロイド」とは何かについて説明していきます。
ステロイドとは「ステロイド核(コレステロール骨格)」という構造を持つ物質を指す言葉であり、実は体内で自然に分泌されている物質でもあります。
「ステロイド」を別の名前で「副腎皮質ホルモン」と呼びます。
私たちの体内にある「副腎」という臓器をご存知でしょうか。副腎は5cmほどの大きさのとても小さな臓器ですが、様々なホルモンを分泌する事によって体の機能や状態を調節する重要な役割を担っています。
ホルモンとは体の別の器官がどのように働くべきかという命令を伝える情報伝達物質のことで、私たちの体はこのホルモンによって命令を出し合うことによって体の状態を常に正常に保っています。
例えば、「インスリン」というホルモンがあります。糖類を多く摂取した時など、私たちの体の血糖値(血液中のブドウ糖の量)が上昇します。すると膵臓(すいぞう)と呼ばれる臓器から「血糖値を下げろ」という命令を持ったインスリンが分泌されます。
この命令を受け取った肝臓や筋肉は血液中のブドウ糖を取り込むように働き、結果として血糖値を下げるのです。このようにして常に血糖値(体の状態)を一定に保っています。
副腎から分泌されるホルモンの中には、アトピーの改善においてとても重要な働きをするものがあります。
副腎は中心部分である「副腎髄質」と外側の部分である「副腎皮質」にわかれており、それぞれ分泌されるホルモンが異なります。この2つのうち副腎皮質から分泌されるホルモンを「副腎皮質ホルモン」と呼び、その中に糖質コルチコイド(グルココルチコイド)という種類があります。
糖質コルチコイドに分類される「コルチゾール」にはアトピーの炎症を抑える働きがあります。そして、この副腎皮質ホルモンに共通しているのが「ステロイド核」という構造です。
アトピー治療で頻繁に使われる「ステロイド薬」はこの構造をもとに人工的に合成し、手を加えることで、人が元々分泌しているステロイドホルモンよりも炎症を鎮める効果を強くしたものを指します。

ステロイドの効果とメカニズム
ステロイドは他の薬に比べて遥かに強力にアトピーの症状を抑えてくれます。
その強力さの理由としては、広大な効果範囲と、炎症を起こす物質を作る過程において、根本の部分に作用するということがあります。しかし、その強力な効果の代償として重大な副作用をもたらすリスクもあります。
その主な作用について説明していきます。
免疫システムに作用して強力な抗炎症作用を発揮する
ステロイド剤の効果としてまずあげられるのは、その強力な抗炎症作用と免疫抑制作用です。
私たちの体には、異物が侵入してきた際に、それを攻撃して排除しようとする「免疫」と呼ばれる仕組みがあります。炎症は、この仕組みによって異物が攻撃される時に放出される化学物質によって自分自身の体も攻撃されてしまうことによって起こります。ステロイド剤は主にこの免疫の働きに干渉することによって炎症を鎮めます。
ステロイドの抗炎症作用には大きく、「遺伝子を介して作用するもの」、「遺伝子を介さず血管に作用するもの」の2つの作用があります。
まずは「遺伝子を介する作用」について説明します。私たちの細胞は、細胞内にある遺伝子の情報をもとに働いています。いくつもある遺伝子情報のうちどの情報が活性化するかによって働きが決まります。
ステロイド剤は細胞内に入り、炎症を抑える働きをする遺伝子を活性化する働きがあります。
詳しく説明していきます。
ステロイド剤は細胞内に入ると、「ステロイド受容体(GRα)」と呼ばれる細胞内にあるステロイド専用の受け皿のようなものと結合し、細胞の核(中心部)に侵入していきます。両者が結合した物質を「ステロイド・GRα複合体」と呼びます。
細胞核の遺伝子の中には、様々な細胞の働きに対するスイッチのようなものがあり、その中にステロイドに反応して炎症を抑える働きをするスイッチがあります。
核内に入ってきたステロイド・GRα複合体は、それらと反応することによってスイッチをONにし、炎症を抑える働きをさせる「サイトカイン」と呼ばれる情報伝達物質を分泌します。サイトカインとは細胞同士での情報伝達物質で、これを放出することによって他の細胞にどのような働きをするのかという命令を伝えているのです。
また、遺伝子の中には細胞に炎症を促進させるサイトカインを分泌させるスイッチもあります。ステロイド・GRα複合体は、そのスイッチをONにさせる物質と結合することによって、スイッチが入るのを邪魔します。その結果、炎症性サイトカインの分泌を抑制するのです。
このように、ステロイド剤は遺伝子に働きかけて、炎症を起こす細胞にその機能を抑制させたり、炎症を起こす機能を増幅させる命令を遮断したりすることで炎症反応を鎮めるのです。

次に「遺伝子を介さずに血管に作用する」働きについて説明します。
ステロイドには、炎症を促進させる物質が血管から体の組織に漏れ出すのを防ぐ働きがあります。
私たちの血管の壁面は通常、水分や水に溶ける性質を持つものだけを通し、血液に含まれているタンパク質や、細胞などは通ることはできません。しかし、炎症が起きると本来通さない物質が血管から漏れ出し炎症を悪化させてしまいます。
炎症が起きると、免疫細胞から分泌される科学物質などの働きによって、血管の壁面の細胞同士のつながりが弱くなり物質が通り抜けやすくなります。
すると、血管内からも異物を攻撃する役割を持った細胞が漏れ出します。これらの細胞は炎症が起きている場所で発生したサイトカインの影響で引き寄せられ、異物への攻撃作用が活性化されます。この時に放出される化学物質にも体を傷つける働きがあるのです。
ステロイド薬には「血管収縮作用」といって、血管壁面の細胞の隙間を閉じる作用があります。その作用によって、炎症を起こす細胞が血管外に漏れ出すのを防いで炎症を軽減させるのです。
このように、ステロイド剤には炎症を起こす物質が血管から漏れるのを抑制し、その結果として炎症反応を抑える作用があります。
ここまで、ステロイド剤の免疫抑制・抗炎症作用の仕組みについて説明してきました。では、アトピー性皮膚炎ではその作用はどのように働いているのでしょうか。
その仕組みを理解するためにまず、免疫によって炎症が起きる流れを簡単に説明していきます。
まず免疫という仕組みを構成する要素として、「樹状細胞」「ヘルパーT細胞」「B細胞」「抗体」「マスト細胞」があります。これらの要素が互いに作用しあって外からの異物と戦っているのです。それぞれの役割を簡単に説明します。
【免疫システムを担う細胞や分子】
 |
【樹状細胞】 | 異物が侵入してきた時に、一番最初に対応する細胞、侵入してきた異物を食べて、「ヘルパーT細胞」に「この異物の正体は何か」ということを伝える働きをします。この働きを「抗原提示」と呼びます。免疫の仕組みの中では斥候のような働きを持っています。 |
 |
【ヘルパーT細胞】 | ヘルパーT細胞は免疫の仕組みを強化する働きがあります。また免疫システムの司令官のような働きをします。樹状細胞によって提示された異物の性質によって、性質が変わり、それぞれ異なる情報をB細胞へと伝えます。 |
 |
【B細胞】 | T細胞から情報を受け取り、抗体と呼ばれる異物を攻撃する物質を作りだします。免疫の仕組みの中では兵隊の訓練所のような働きをします。 |
 |
【抗体】 | B細胞によって作り出され、異物を攻撃する物質です。免疫の仕組みの中では兵隊の役割をするものです。抗体の中にはIgE、IgG、IgAというように複数の種類があり、それぞれ働きが異なります。ここでは最も代表的なIgE抗体について説明します。 |
 |
【マスト細胞】 | 異物を攻撃するためのヒスタミンやロイコトリエンと呼ばれる化学物質を含んだ細胞でIgE抗体を介して異物と反応するとこの化学物質を放出して攻撃します。この化学物質が炎症の元にもなります。IgE抗体は単体では異物を攻撃することができません。そのためマスト細胞と協力して異物を攻撃するのです。 |
 |
【好酸球】 | アレルギー遅発型反応で活躍する細胞です。細胞中に含まれる顆粒の中には、組織を傷つける酵素が多く含まれます。 |
 |
【好塩基球】 | マスト細胞とほぼ同じ働きをする細胞です。 |
上記の表で紹介したように、免疫の仕組みは多くの細胞などの働きが関係しています。ここから免疫によって炎症が起こる一連の流れについて説明します。
体内に異物が入ってくると、まず「樹状細胞」という細胞が異物を取り込み、それの性質を「ヘルパーT細胞」に伝えます。このことを「抗原提示」(図中①)と言います。
ヘルパーT細胞とは免疫の仕組みを強化する細胞で免疫の仕組み全体の司令塔の役割を果たす細胞です。ヘルパーT細胞には主なものに1型と2型という2つに分けられ、それぞれ担当する働きが異なります。1型は主に細菌やウイルスを退治するための細胞で、2型はアレルゲン(アレルギーの原因物質)を退治するための細胞です。
樹状細胞からの抗原提示によって得た情報によってT細胞から、後述する「B細胞」に抗体を作るような命令を持ったサイトカインを分泌します(図中②)。
サイトカインによってT細胞からの命令を受けっとったB細胞は、その命令によって対応する抗体を作り出します(図中③)。抗体とは異物を攻撃するための物質を指します。この時にアレルゲンを退治するために作り出される抗体がIgE抗体です。
しかし、このIgE抗体は「抗体」という名前を持っているものの、それ単体ではアレルゲンを攻撃することができません。そこで活躍するのが「マスト細胞」と呼ばれる細胞です。
このマスト細胞は内側に「ヒスタミン」や「ロイコトリエン」と呼ばれる科学物質を蓄えていて、IgEを介してアレルゲンと接触することによってこの化学物質を放出しアレルゲンを攻撃します。この時に放出される「ヒスタミン」や「ロイコトリエン」が炎症を起こすのです。

ステロイド剤はこの一連の仕組みの中で、まずT細胞からサイトカイン(IL-4)が分泌されるのを抑制します。B細胞はこのサイトカインを受け取らないとIgE抗体を作り出すことができません。
さて、ここまで説明してきたのは炎症の始まりの部分であり、炎症反応には続きがあります。
炎症が起きると、さらに効率よく抗原を排除するために、別の炎症細胞である「好酸球」や「好塩基球」などの「白血球」を呼び寄せ、その働きを活性化させます。これらの働きは主にマスト細胞から分泌される、ヒスタミンなどの化学物質とサイトカインによっておこされます。
炎症が起きると、ヒスタミンなどの効果によって血管の壁面の細胞同士のつながりが緩み、血液中の成分が血管の外に漏れ出しやすくなります。すると炎症箇所で分泌されているサイトカインの作用によって、引き寄せられるように「好酸球」や「好塩基球」が集まっていきます。
引き寄せられた好酸球や好塩基球は、サイトカインの影響によって活性化し、細胞内にある酵素や化学物質を放出することで抗原を攻撃します。これらの働きによって、炎症反応に拍車がかかるのです。
ステロイド剤はすでに説明してある「血管収縮作用」によって、「好酸球」や「好塩基球」が血管外に漏れ出すのを防ぐと同時に、これらの炎症細胞を引き寄せ、活性化させるサイトカインが分泌されるのを抑制します。

【アトピー性皮膚炎におけるステロイド外用薬の作用箇所】
本文中で説明した作用の他にも、ステロイド剤は免疫システムのあらゆる箇所に作用します。その作用箇所を下記にまとめます。
①血管透過性亢進抑制
②T細胞からのサイトカイン産生抑制
③好酸球の浸潤、活性化抑制
④マクロファージからのサイトカイン産生抑制
⑤マクロファージの浸潤、活性化抑制
⑥マスト細胞からのPG、LT産生抑制
⑦マスト細胞からのサイトカイン産生抑制
⑧樹状細胞の抗原提示能抑制
ステロイド剤は免疫の仕組みにおいて、あらゆる箇所で炎症を促進させる働きを妨害し、また、炎症を抑える仕組みを強くすることで、強力な抗炎症作用を発揮しているのです。
細胞増殖抑制作用
もう一つの作用は、過剰な炎症を起こす原因となる細胞や白血球などの免疫細胞を死に追いこむ作用です。この作用によって炎症反応を終わらせ、症状を鎮めます。
私たちの体の細胞には元々自分自身を死に追い込む機能がプログラムされており、その機能を「アポトーシス」と呼びます。私たちの体は、体内で異常をきたしたり、働きを終えたりした細胞はこのプログラムによって自殺させることで、正常な体を維持しています。
例えば癌(がん)などがわかりやすい例です。私たちの体内で癌化した細胞は、このアポトーシスによって除去され続けることによって、腫瘍となることを未然に防いでいます。
炎症を起こしている細胞や白血球も、体外からの異物を排除し終わると、自分自身を死に追いやり、その働きを終えます。ステロイド剤にはこの自殺を促進させる働きがあります。
ステロイド剤によって遺伝子に影響を受けた細胞は、自身が癌化したり、異常な働きをしたりすることを避けるためにアポトーシスが起こるのです。
このようにして炎症を起こしている細胞の死を早めることで、炎症反応を鎮めます。
炎症物質を作り出す仕組みを妨害する
次に「脂質から炎症物質が作られる仕組みに作用する」働きについて説明します。この働きは免疫とは関係のない働きです。
私たちの体には食事から得た脂質をもとに、炎症を起こす物質を作り出す仕組みがあります。ステロイド剤はこの仕組みを妨害することによって、炎症を起こす物質が作られるのを抑制します。
私たちが食事などから摂取している油は幾つかの種類に分類することができ、その中にリノール酸という種類の油があります。このリノール酸は分解されて「アラキドン酸」という物質へ変わり、細胞膜に蓄積されます。
この蓄積されたアラキドン酸は、幾つかの酵素(体内での化学反応を促進する物質)の働きによって形を変え最終的に「プロスタグランジン」や「ロイコトリエン」という炎症を促進させる働きを持つ物質へと変換されます。この一連の流れを、アラキドン酸をもとに滝(カスケード)のように様々な反応が起こることから「アラキドン酸カスケード」と呼びます。
この反応は、まず酵素の働きによって、細胞膜からアラキドン酸が切り離されることから始まります。ステロイド剤にはこの酵素の働きを抑制する働きがあります。このカスケード反応を最上流から抑制することによって、炎症を促進する物質が作られるのを抑制することができるのです。

ステロイド剤は免疫以外の機能にも作用し、炎症物質を作り出す仕組みを妨害することによって炎症を抑える働きをします。
ここまで説明してきたように、ステロイド剤は免疫のあらゆる仕組みを抑制したり、炎症物質ができる仕組みを遮断したりなど、とても広範囲に作用します。このことによってステロイド剤が協力な抗炎症剤と言われるのです。
しかし、この作用にはデメリットも存在します。免疫とは体外の細菌やウイルスから身を守る仕組みでもあります。この仕組みを抑制するということは、細菌やウイルスに感染しやすくなるということです。
そのため、ステロイド剤を長期連用していると、感染症を起こしやすくなり、アトピーの場合はとびひなどを合併しやすくなります。
ステロイド剤には依存性がある
ところで、ステロイド剤には「一度使ったら止められない」依存性があると聞いたことはありませんか。その理由としては下記の3つが挙げられます。
徐々にステロイドが効かなくなってくる
ステロイド剤は長期間使用していると、その効果が弱くなっていきます。そのため、徐々に強いランクのステロイド剤を使用しなくては症状が抑えられなくなっていきます。
ステロイド剤の抗炎症・免疫抑制作用は細胞内にある「ステロイド受容体(GRα)」という受け皿に乗ることによって効果を発揮します。ステロイドを長期間使用しているとこの受け皿が細胞内に発生しにくくなってしまいます。
それと同時に「デコイ受容体(GRβ)」と呼ばれるステロイドの効果を阻害してしまう物質が作られるようになります。そのため炎症を抑える効果が弱くなってしまうのです。
また、ステロイド剤による血管収縮作用も弱くなります。
ステロイド剤によって収縮した血管は、その反動で拡張しようとする働きがあります。この働きと拮抗することによって、徐々にステロイドの血管収縮作用が弱くなってしまうのです。
このように、ステロイド剤は使用回数を重ねるごとに効果が弱まっていきます。
そのため、炎症を抑えるためにより強いランクのステロイド剤を必要とするようになるのです。
アレルギー体質への変化
ステロイド剤を長期間使用し続けていると、アレルギーの原因物質に過剰に反応する体質になっていくことがあります。
私たちの免疫機能には、「細菌やウイルスを撃退する」ものと、「アレルゲンなどの異物を撃退するもの」の2種類があります。前者を担当するのが1型T細胞(Th1)で、後者を担当するのが2型T細胞(Th2)です。
この二つの免疫細胞はお互いの増殖を抑制するための命令を出すサイトカインを分泌し、足の引っ張り合いをして陣取り合戦をしています。そのためどちらかの勢力が強くなると、もう片方が弱くなる性質があります。
例えば、過剰な清潔志向の親の元で育った子供は、幼少期に細菌に触れる機会が少ないため1型T細胞の活躍する機会が多くありません、しかし、アレルゲンとなる物質はいたるところに存在しているため、2型T細胞ばかりが活躍、増殖することでアレルギー体質に偏っていくことがあります。
ステロイド剤の免疫抑制作用は、1型と2型のどちらも抑制します。しかし、その抑制作用には差があり1型の方をより強く抑制してしまいます。
そのため、長期間の連用をおこなうと2型のT細胞の方が優勢になって、アレルギーを起こしやすい体質へと変わっていくのです。
このように、ステロイド剤の連用はアレルギー体質を作ってしまいます。そのためそのアレルギー反応を抑えるために、さらにステロイド剤を使うという循環が起こるのです。
ステロイド皮膚症への移行
ステロイドは、一旦アトピーの症状を抑えてくれますが、その効果の裏でアトピーを悪化させてしまう事もあります。その原因が「酸化コレステロール」です。
ステロイドホルモンはコレステロールから合成されたものです。強力な炎症作用を発揮したステロイドは、酸化されて酸化コレステロールになります。
この酸化コレステロールは通常は尿から排出され、さらに酸化の度合いが強くなると肝臓で分解されて腸から排出されます。そのため少量の使用ならば問題は起きません。
しかし長期の利用によって酸化コレステロールが過剰に発生した場合、処理が間に合わなくなり血管壁や皮下脂肪などの組織に蓄積されていきます。この蓄積された酸化コレステロールには炎症を起こす作用があります。
この炎症作用は、ステロイド剤の抗炎症作用よりも弱いため、ステロイド剤を塗れば治ります。しかし、塗らなければ炎症が起こるため、塗り続けているうちに酸化コレステロールがどんどん蓄積されていき、炎症作用が大きくなり続けるのです。
このようにステロイド薬は炎症を起こす働きの他に、炎症を起こしてしまう作用もあり、その炎症作用はステロイドを連用するほど大きくなります。そのため、大きくなった炎症作用を鎮めるために、より強いランクのステロイド剤を使うという負のループに陥るのです。
ここまで説明してきたように、ステロイド剤は長期間使用していると、効果が弱まり、さらにステロイドの作用によって体が炎症を起こしやすくなってしまいます。
そのため、炎症を抑えるためのステロイドが、返って炎症を起こし、その炎症を抑えるためにまたステロイドを塗るという、イタチごっこになってしまうのです。これがステロイドに依存性があると言われる理由です。
ステロイドの種類(強さ)
ステロイド剤は、日本においてはその効果の強さによって、「ウィーク(弱い)」「マイルド(普通)」「ストロング(強い)」「ベリーストロング(とても強い)」「ストロンゲスト(最強)」の5段階に分類されており(米国では7段階)、使用する場合には、症状の度合いや、発症している部位によって慎重に選ぶ必要があります。
| 薬の強さ | 商品名 | 成分名 | 一般的な使用期間 |
|---|---|---|---|
| 1群
strongest (最強) |
デルモベート | プロビオン酸クロベタゾール | 【大人】…連続使用は1週間以内
【子供】…体に吸収されやすい成分のため、原則使用不可 ※ステロイド剤の中で最も吸収されやすい成分が使用されています。 |
| ジフラール | ジフロラゾン酢酸エステル | ||
| ダイアコート | 酢酸ジフロラゾン | ||
| Ⅱ群
very strong (非常に強力)
|
トプシム | フルオシノニド | 【大人】…連続使用は1週間以内。体幹部に使用されます。
【子供】…使用は数回まで。腕や足などの四肢に使用されます。 |
| アンテベート | 酪酸プロピオン酸ベタメタゾン | ||
| ネリゾナ | 吉草酸ジフルコルトロン | ||
| ビスダーム | アムシノニド | ||
| フルメタ | フランカルボン酸 | ||
| メサデルム | ブロビオン酸デキサメタゾン | ||
| マイザー | ジフルブレドナート | ||
| Ⅲ群
strong (強力)
|
ブロバデルム | ブロビオン酸べクロメタゾン | 【大人】…連続使用は2週間以内。全身〜体幹部限定で使用されます。 【子供】…連続使用は1週間以内。顔、陰部を除く体幹部に使用されます。 |
| ボアラ | 吉草酸デキサメタゾン | ||
| リンデロン-V/リンデロン-VG | 吉草酸ベタメタゾン | ||
| Ⅳ群
medium (中程度)
|
リドメックス | 吉草酸酢酸ブレドニゾロン | 【大人】…連続使用は2週間以内。全身(顔を含む)に使用されます。 【子供】…連続使用は1週間以内。全身(顔を含む)に使用されます。 |
| ロコイド | 酪酸ヒドロコルチゾン | ||
| キンダベート | 酪酸クロベタゾン | ||
| アルメタ | ブロビオン酸アルクロメタゾン | ||
| Ⅴ群
weak (弱い) |
ブレドニン | 酢酸ブレドニゾロン | 【大人】…連続使用は2週間。全身(尻や陰部を含む)に使用されます。 【子供】…大人と同じ。 ※成分は吸収されにくいですが、含有量は多いので注意が必要です。 |
| テラ・コートリル | ヒドロコルチゾン/クロタミトン | ||
| コルテス | 酢酸ヒドロコルチゾン |
上記にそれぞれのランクのステロイド剤の特徴をまとめました。ステロイド剤はそのランクによって、安全とされる試用期間や、使用してはいけない部位などがあります。
誤った選択をすると副作用を起こす危険性があります。もしも使用する場合は慎重に選択するようにしましょう。
ここまでを通して、ステロイド剤とは何かということについて説明してきました。
ステロイド剤は強力な抗炎症剤ではありますが、その強力な薬効故に重大な副作用をもたらす可能性もあります。そのため扱いには慎重にならなければなりません。
冒頭にも述べたように、アトピーを治すのはあなた自身です。医師の診断を信用するのは大切ですが、全て丸投げではいけません。
ステロイド剤を使用する場合はあなた自身も薬について学ばないといけません。
仮にステロイド剤の不適切な使用によって副作用が起きた場合、医師を訴えることはできるでしょう。勝つこともできるかもしれません。しかし、医師を訴えたからといって、副作用が治る訳ではありません。
ステロイドに対する知識を身につけることで、副作用のリスクを減らすことができます。また、知識を身につけることで、医師に質問することができるようになり、医師との信頼関係を深めて安心して治療に専念することができるというメリットがあります。
ステロイド剤の使用に対して受け身になるのではなく、慎重に使用するようにしましょう。