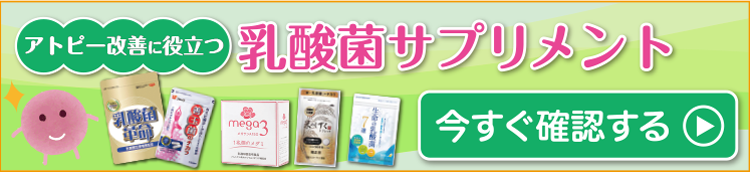アトピーとはは私たちの体に備わっている「免疫力」が、何らかの原因によって過剰に働くことで起こる疾患です。免疫とは、私たちの体の中に侵入してくる異物に対して、それが有害か否かを判断し、有害であれば攻撃して排除する仕組みを指します。
ところで、皆さんはアトピーの治療のために病院に行ったり、様々な本や情報サイトを見ていると「免疫力を上げてアトピーを治そう」という旨の情報を目にすることがあると思います。
そして、「アトピーの原因が免疫力ならば、免疫力を上げると返ってアトピーが悪化するのではないか」と矛盾を感じたことはありませんか?
調べたことのある方ならばご存知でしょうが、アトピーの治療で必ずと言っていいほど用いられる「ステロイド剤」はそもそも免疫力を抑える薬です。
アトピーを治すためには、免疫力は「上げるべき」か「下げるべき」か、いったいどちらが正しいのでしょう。
結論から言うと、どちらも正しくありません。アトピーを治すためには、免疫力は「調整」するのが正解です。バランスの崩れた免疫力を調整しつつ上げていくことで、アトピーを治しさらに健康な体へ導くことができます。
少し難しい話ですが、このページでは、複雑な免疫システムと、それを調整するという概念についてわかりやすく説明していきます。
目次|このページでわかること
アトピーは免疫システムの乱れによって起きる
私たちの体には、体の外から様々な有害物質(細菌・ウイルス・アレルゲンなど)が入ってきたときに、これらを攻撃して排除したり、体内で無害化したりする仕組みが備わっています。
この仕組みのことを「免役」と呼び、これによって私たちは体の外の有害物質から守られており、免疫がないとわたしたちは生きていくことができません。
このように、本来は私たち体にとって有益な作用をもたらす仕組みですが、何らかの原因によってこの仕組みが乱れてしまうことがあります。このことによって、本来ならば無害なものに反応してしまったり、過剰に働いたりしてしまい、私たちの体自体に牙を向いてしまうことがあります。
すると、私たちの体の組織が炎症を起こしてしまうことがあります。仮に、それが喉や鼻に現れれば、花粉症などになり、皮膚に現れれば蕁麻疹やアトピー性皮膚炎となるのです。
例えば、夏に蚊が血を求めて寄ってくると、みなさんは払いのけるか、もしくは叩いて蚊を退治しようとすると思います。しかし、この時にあまりに強く叩きすぎるとどうでしょう。
うっかりしてあまりにも強い力で叩くと、蚊を退治するどころか自分自身も強く叩きすぎることによって、叩いた場所はヒリヒリと痛みを感じるようになります。
同じように、アトピーとは、体の外からの異物や有害物質に対して、防衛しようとする仕組みが過剰に反応してしまい、自分自身も傷つけてしまう現象なのです。この例で言うと、アトピーは免疫システムの慢性的な「うっかり」と言えます。
このように、アトピー性皮膚炎は、私たちの体に備わっている「免疫システム(免疫系)」のバランスが崩れることによって起こります。
この後に、免疫の仕組みについてさらに詳しく説明していきます。
免疫系の仕組み
アトピーとは免疫システムの乱れによって起こるということはすでに述べました。ここからさらに詳しく説明していきます。
免疫システムはいくつもの「免疫細胞」が複雑に連携しあって構成されています。
まず、この複雑極まる仕組みの構成要素である免疫細胞とそれらの持つ役割について下記の表詳でしく説明します。本文を読み進める上で、理解しにくくなったら戻って見直すといいでしょう。
【免疫の仕組みを構成する細胞たち】
| イメージ | 名称 | 働き |
 |
マクロファージ | 免疫システムの中で、最も基本的、かつ中心的な活躍をする細胞です。 体内に異物が侵入してくると、最も早く反応して、その異物を取り込み、細胞内の酵素で分解します。 また、取り込んだ異物の情報を細胞の表面に提示してT細胞に伝える働きをします。 |
 |
樹状細胞 | 皮膚や粘膜に広く存在する細胞で、マクロファージと同様に、一番最初に活躍し異物を取り込む細胞です。 また、自身が取り込んだ異物の情報や、マクロファージが吸収した異物の情報を、リンパ節に持ち帰って「T細胞」に伝える役割を担っています。 この働きを「抗原提示」と言います。 |
 |
T細胞 | 免疫の仕組みの中で司令塔となる働きをする細胞です。樹状細胞からの抗原提示によって受け取った情報によって、性質の違うT細胞へと変化していきます。また、変化後のT細胞はそれぞれ異なった種類の命令物質(サイトカイン)を「B細胞」に伝えます。 |
 |
B細胞 | T細胞からの命令を受け取り、その情報によって、種類の異なる「抗体」を作り出します。 |
 |
抗体 | B細胞によって作り出される、異物撃退用の物質。攻撃対象によって、IgE、IgA、IgGなど複数の種類が存在します。 |
 |
マスト細胞 | 細胞の内側に「ヒスタミン」やロイコトリエン」という化学物質を蓄えています。 IgEを介して異物と接触することで、これらの化学物質を放出し排除しようとします。 |
 |
好酸球 | 免疫システムの中で、援護役を果たす細胞です。マスト細胞が化学物質を放出するときに出す命令物質に引き寄せられて集まり。炎症を加速させます。 |
 |
好塩基球 | 好酸球と同様に援護役をする細胞で、マスト細胞とほぼ同じ働きをします。 |
自然免疫と獲得免疫
まず最初に、私たちの体にある免疫の仕組みには「自然免疫」と呼ばれるものと、「獲得免疫」と呼ばれるものの2つの系統があります。
それぞれ順番に説明していきます。
自然免疫
自然免疫とは、体の中に異物や有害物質が侵入してきた際に真っ先に働くシステムです。このときに働く細胞が「マクロファージ」という細胞です。
マクロファージは別名「貪食細胞」と呼ばれる細胞で、体の外から侵入してきた異物や、体内で発生した老廃物に対して、真っ先に反応して向かいます。そして、その異物を取り込み、消化することによって無害化するのです。この働きを「食作用」と言います。
さらに、マクロファージは異物を取り込んだ後に、「サイトカイン」と呼ばれる細胞同士の情報伝達物質を分泌して、他の炎症細胞(好中球などの白血球)を活性化させることで、より早く異物を除去しようとします。つまり、マクロファージ単体では異物の除去が非効率な為、応援となる細胞を呼び寄せ効率よく除去しようとするのです。
このように、自然免疫とはマクロファージが異物を消化することによって無害化する仕組みで、もっとも基本的な免疫システムです。そして、全ての免疫の働きはマクロファージから始まっています。
獲得免疫
続いて、「獲得免疫」について説明していきます。
獲得免疫とは私たち人間や哺乳類など、高等な生物が進化の過程で、より効率よく体を防衛する為に身につけた免疫システムです。これは同じ異物や有害物質が侵入してきたときに、2回目以降、それを効率よく撃退する仕組みです。
先ほど、マクロファージの説明として「食作用」を挙げました。しかし、マクロファージには獲得免疫において重要な働きがもう一つあります。
異物を取り込んだマクロファージは、その異物の情報を「樹状細胞」に伝えます。樹状細胞とは皮膚や粘膜に広く存在している細胞で、マクロファージと同様に侵入してきた細胞を取り込みます。
さらに、それと同時に、自身が取り込んだ異物や、マクロファージから分泌されるサイトカインによる情報を、リンパ節という免疫の前線基地のようなところに持ち帰ります。そして、その情報を「ヘルパーT細胞」に伝えるのです。この働きを「抗原提示」と呼びます。
T細胞は抗原提示によって運ばれてきた情報の性質によって「1型ヘルパーT細胞(Th1)」と「2型ヘルパーT細胞(Th2)」の2つの種類に変化し、次の「B細胞」という免疫の現場の司令官の細胞に対して、その働きを指示するサイトカインを分泌するようになります。
リンパ節が免疫の前線基地ならば、ヘルパーT細胞は免疫の司令官といったところでしょうか。
前者は主に細菌やウイルスを相手に戦う細胞で、後者は主にアレルゲン(アレルギー原因物質)を相手に戦う細胞です。このどちらに変化するかによって、この後の免疫の働きが変わってきます。
細菌やウイルスが侵入してきた場合、1型に変化したT細胞からのサイトカインを受け取ったB細胞は「IgG」という抗体を作り出して、細菌を攻撃します。「抗体」とはB細胞から作られる、細菌などの異物を攻撃する物質です。これによって、細菌を破壊して撃退しているのです。
このときに、変化したB細胞やT細胞はリンパ節に長く留まります。その為、2回目以降に同じ細菌が侵入してきたときには早く効率よく細菌・ウイルスを撃退できるのです。
水疱瘡などが一度かかったら、2度目以降かからなかったり、はしかの予防接種をすると、それ以降はしかにかからないのは、この獲得免疫によって、特定の最近に対する免疫力を身につけるからです。
また、樹状細胞がリンパ節に持ち帰った情報が、細菌ではなく、アレルゲンによるものだった場合はT細胞は2型に変化します。2型に変化したT細胞からの指示を受け取ったB細胞は、IgGではなく、「IgE」という抗体を作り出します。
このIgE抗体ですが、それ単体には異物を攻撃する能力はありません。IgE抗体は皮膚や粘膜に数多く存在し、内側に異物攻撃用の化学物質(「ヒスタミン」「ロイコトリエン」)を蓄えた「マスト細胞(肥満細胞)」に結合することによってその効果を発揮します。
マスト細胞の表面にはIgE抗体と強くくっつく性質を持つ「IgE受容体」という物質が非常に多く存在しています。マスト細胞に連結したIgE受容体がアレルゲンに結合すると、IgE受容体が刺激されます。この刺激をきっかけとして、マスト細胞は内側にある「ヒスタミン」や「ロイコトリエン」を放出するのです。
このヒスタミンやロイコトリエンには、アレルゲンとなる異物を攻撃するだけでなく、皮膚組織に炎症を起こしたり、かゆみを感じさせる元になったりします。
この反応によって、アトピーのかゆみや、炎症が起きるのです。
このように私たちの体に備わっている免疫システムには「自然免疫」と「獲得免疫」の二つの系統が存在します。
大まかに言うと、この獲得免疫のうち2型のT細胞を起点としてはじまる一連の反応が、アトピーのようなアレルギーや炎症のメカニズムになります。
アトピーの正体は「1型T細胞」と「2型T細胞」のバランスの乱れにある
ここまでの説明の中で、アトピーの症状の元になる、「獲得免疫」について述べました。
過去の私と同じようにみなさんを悩ませているアトピーの原因は、この獲得免疫の中で活躍する、「1型T細胞(Th1)」と「2型T細胞(Th2)」のバランスの乱れにあります。
細菌やアレルゲンなどの異物が侵入してきたことによって、1型と2型に変化したT細胞は、免疫の前線基地であるリンパ節に長い間留まります。そして、再び同じ種類の異物が侵入してきた時に活躍するのです。このことによって、2回目以降の有害物質の侵入に対して、1から免疫反応を繰り返さなくても効率よく対処できるような仕組みになっているのです。
ところで、1型と2型のT細胞ですが、B細胞に対するサイトカインの他に、お互いがお互いの増殖を抑える働きを持つサイトカインを分泌しています。どちらかの細胞が増殖すると、もう片方の細胞の勢力が少なくなると言うような陣取り合戦をしているのです。

例えば、過剰な清潔志向の親のもとで幼少期を過ごした子供は、細菌やウイルスに接する機会が圧倒的に少なくなります。ところが、アレルゲンとなる物質はいたるところに存在するため、体内でTh2ばかりが増殖して優勢にになってしまいます。すると、なんらかのアレルギー体質になってしまうのです。
つまり、Th1とTh2の2つのT細胞の勢力バランスが崩れて2型の細胞が優勢になってしまうと、アトピーのような炎症反応を慢性的に起こしやすい体質になるのです。
これが大まかに捉えたアトピー性皮膚炎のメカニズムです。

免疫力は高めるのではなく「調整」するのが正解
さて、漢方などを自然な方法でアトピーを治すような本や情報サイトを見ていると、「免疫力を高めてアトピーを治そう」という趣旨の情報を見かけることがあります。
ここで、多くの人は「免疫力を高めたら帰ってアトピーの症状が悪化するのではないのか?」と疑問を持つことでしょう。
実際、アトピーの治療で必ずと言っていいほど使用される「ステロイド剤」や「プロトピック」は免疫力を抑える薬です。
しかし、免疫力を「ただ」高めることも、抑えることも、どちらも正しくありません。免疫力は「調整」するのが正解なのです。
先ほど、アトピーの原因がTh1とTh2の勢力バランスが崩れることによって起きると説明しました。そうであるならば、これらのバランスの崩れを整えて2型のT細胞が過剰に働く状態を改善するべきなのです。
ここで注目するのが、Th1とTh2のほかに存在する、第3のT 細胞である「制御性T細胞(Th3)」です。
制御性T細胞にはその名の通り、Th1やTh2が過剰に活性化するのを抑えて、免疫システムのバランスを整えるくれる働きがあります。この制御性T細胞の勢力を強くすることによって、アトピーのような免疫が過剰に働区ことで起きる疾患を抑えてくれるのです。
例えるならば、Th1とTh2は車の前進と後退のアクセルであり、制御性T細胞はブレーキでしょうか、前進と後退のどちらのアクセルも車を運転する上では必要不可欠な機能です。しかし、抑えがきかずに暴走を始めると危険な状況を招くことになります。そのため、スピードを制御するブレーキが必要になるのです。
このように、アトピーの治療において「免疫力」は、ただ上げるだけならば当然かゆみや炎症は進行します。そして反対にステロイドなどの免疫抑制剤を用いて免疫下げると、一時的にはいいかもしれませんが、細菌やウイルスへの抵抗力も下がるため、感染症などを合併しやすくなってしまいます。
免疫力は、その乱れを「調整」しバランスを取りながら上げるのが正しいアプローチであると言えます。
まとめ
ここまで、アトピーの原因である免疫システムの乱れについて詳しく説明してきました。
アトピーは免疫細胞のうち、細菌担当の細胞とアレルゲン担当の細胞の勢力が乱れて、後者が優勢になり、過剰に働くことによって起こります。
これを治すためには、単に免疫力を上げたり、ステロイドなどの免疫抑制剤で、闇雲に免疫力を下げたりしてはいけません。どちらも、あなたにとってマイナスの結果をもたらします。
少し自分の話をしますと、私は子供の頃、アトピーの症状を抑えるためステロイド剤を使用していました。これによって確かに一時的に症状は改善しましたが、「とびひ」という感染症にかかり、返って症状は悪化してしばらく寝たきりになってしまいました。とびひによる湿疹はただのアトピー炎症と違って、痛みも伴うため二重苦だったことを覚えています。
このように、免疫力を無闇に下げたりすると、返ってアトピーに悪影響を及ぼすおそれがあります。アトピーは乱れた免疫力を調整するという意識を持ちましょう。
私たちの体には先述のTh1とTh2の他にそれらの過剰な活性化を抑える「制御性T細胞」がいます。この勢力を増やすことで、過剰に働いている免疫細胞を抑えることができるようになります。
では、具体的はどのようにしたらいいでしょうか。
意外だと驚かれる方もいるかもしれませんが、答えはは私たちの「腸」にあります。腸は「人体最大の免疫器官」とも呼ばれており、体の免疫細胞の約70%以上が腸に集中しています。腸内環境が良い状態であると、そこに存在する免疫細胞が、バランスを取るように働くのです。そのため、この腸にアプローチすることが、アトピー改善において最も近道であると言えます。腸の状態を健康に保つことがアトピーの根本治療につながるのです。