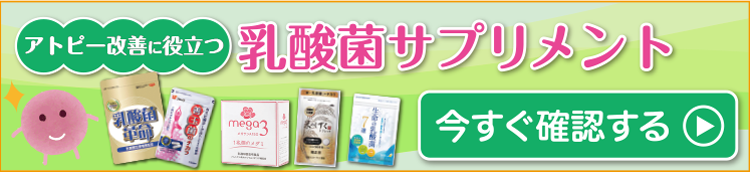私たちの体の中にある「副腎(ふくじん)」という臓器をご存知でしょうか。副腎とは腎臓(じんぞう)の上に位置する小さな臓器です。この臓器はアトピーを克服するためにとても重要な役割を持っています。副腎の働きを促進することでアトピーは格段に改善しやすくなります。
このページではアトピーに関する副腎の働きと、副腎の機能を強化する方法について説明します。
目次|このページでわかること
副腎は体の異常を調節する器官
「副腎(ふくじん)」とは、大きさわずか5cmほどの小さな器官ですが、ホルモンという物質を作りだして体の機能や状態を調節する重要な働きをします。
そして、アトピーに関しても重要な役割を持っています。
ホルモンとは、血液や体液によって身体中に運ばれ、別の器官がどのように働くべきかを伝える情報伝達物質のことです。私たちの体はホルモンを介して命令を出し合うことによって機能しています。ホルモンを分泌する器官は他にもありますが、中でも副腎は体の中の異常に対抗して他の器官の働きを調整することで、体の活動を正常に維持するという役割を担っている重要な器官です。
例えば、甘い物を摂りすぎて血糖値が上がりすぎると、膵臓(すいぞう)から「インスリン」と呼ばれる、血糖値を下げるホルモンを過剰に分泌してしまう場合があります。血糖値が下がりすぎると、体や脳の活動に必要なエネルギーが不足するので、これは異常事態といえます。
この異常事態に対して、副腎は「抗インスリンホルモン」という、血糖値を上げるホルモンを分泌することで、血糖値を正常に戻そうと調整するのです。
この副腎の調整機能はアトピーに対しても重要な役割を果たします。アトピーによる皮膚の炎症は体にとって異常なことです。この異常に対しても副腎が働き正常な状態に戻そうとするのです。
アトピーの炎症を抑える「副腎皮質ホルモン」
副腎から分泌されるホルモンの中には、アトピーの改善において極めて重要な働きをするものがあります。
副腎は中心部分の「副腎髄質」と外側部分の「副腎皮質」とに分かれており、それぞれ作るホルモンが異なっています。2つのうち副腎の外側を覆う、副腎皮質から分泌されるものを「副腎皮質ホルモン」といい、これにはアトピーの炎症を抑える効果があります。

副腎皮質から分泌されるホルモンのひとつに、前述した抗インスリンホルモンでもある「グルココルチコイド」という種類があります。グルココルチコイドの一つである「コルチゾール」というホルモンには、血糖値を調節する働きの他に、体で起きている炎症を抑える効果があります。つまり、アトピーの症状を鎮めてくれるのです。
コルチゾールのような、副腎皮質から分泌されるホルモンの事を別名で「ステロイドホルモン」とも呼び、「ステロイド核」という共通の構造を持っています。アトピーの治療で、炎症を抑える薬として頻繁に用いられるステロイド剤は、コルチゾールの構造を元に人工的に合成し効果を強めたものです。
このように、副腎皮質ホルモンはアトピー改善には欠かせない物質なのです。
副腎の機能低下がアトピー悪化の原因になっている可能性がある
このように、副腎は炎症を抑えるホルモンを分泌する重要な器官です。そのため、何らかの原因で副腎の機能が低下すると、アトピーの症状を抑えられなくなり悪化させてしまうことがあります。
その原因について説明していきます。
副腎疲労症候群
一つ目は、副腎を酷使し過ぎることによって、疲れてしまったために副腎皮質ホルモンの分泌が低下するパターンです。これは、主に食生活の乱れや過剰なストレスによって起こります。
アトピーの炎症を抑える「コルチゾール」には、その他にも下がりすぎた血糖値を正常に戻すなどの働きがあります。こうした炎症を抑えること以外にコルチゾールを使用しすぎてしまうと、副腎は酷使され働きが低下してしまうのです。
例えば、食事をすると私たちの体内では一時的に血糖値(血液中のブドウ糖の量)が上昇します。すると、膵臓(すいぞう)からインスリンという血糖値を下げる働きのあるホルモンを分泌し血糖値を正常に戻そうとします。
通常の食事であれば問題はありませんが、甘いものを大量に食べた場合などは、血糖値は急激に上昇することになり、上がりすぎた血糖値を下げようとしてインスリンの分泌量が急増します。急激に大量のインスリンが分泌されると、正常な値に戻ってからも血糖値が下がり続けてしまいます。
すると、体は危機感を感じてコルチゾールを分泌し血糖値を上げようとします。私たちの体は、このような仕組みによって血糖値を一定に保っています。また、ストレスを感じた時にもコルチゾールは使われます。
甘い物を頻繁に食べるような食生活を続けていたり、ストレスを頻繁に感じていたりすると、副腎はコルチゾールを常に分泌し続けることになります。その結果、疲労が蓄積して機能が低下していくのです。このことによって副腎が疲れてしまった状態を「副腎疲労症候群」と言います。
この副腎疲労には、初期段階にわかりやすい自覚症状があります。それは「朝に弱くなる」ということです。
コルチゾールの分泌量には「日内変動(にちないへんどう)」と呼ばれる一定のリズムがあります。正常な状態であれば、コルチゾールは早朝に最も活発に分泌され、昼までに落ち着いていき、夕方以降はほとんど分泌されないというリズムがあります。
これは、人間が日中に活動するので、起きて活動している昼間にストレスを受けやすいためです。コルチゾールを分泌して目覚めを促し、日中のストレスに備えるのです。
副腎の機能が低下してくると、この日内変動のリズムが乱れ、本来は活発に働かない午後にピークが現れます。その反対に本来活発に働くはずの朝に働かなくなります。そのため夜は興奮して眠れず、朝はなかなか起きられないということになるのです。
アトピーが悪化して炎症が治まらない時に、朝も起きられないと感じたら副腎疲労の可能性があります。食生活を見直したり、ストレスを抱えていないかを考えてみたりしましょう。
ステロイド剤長期服用時の機能低下
もう一つは、副腎を使わないことで機能が衰えていくパターンです。これはステロイド剤の長期間の使用によって起こります。ステロイド剤を長く使い続けることによって、外から副腎皮質ホルモンが補給されることになります。その結果、副腎はホルモンを分泌しなくなり、機能が衰えていくのです。
副腎皮質ホルモンの分泌量は脳の「視床下部」という部分によって調節されています。視床下部とはホルモン分泌を調整する器官です。
この器官は、体で炎症が起きるとコルチゾールを平常時よりも多く分泌するように副腎に命令します。反対に分泌量が多すぎるとその量を減らすのです。このような働きによって、体内のコルチゾールの濃度は一定に保たれているのです。
すでに説明したようにステロイド剤は、副腎皮質ホルモンの構造を模倣して人工的に作られたものです。ステロイド剤を使用することで体内のステロイドホルモンの濃度が高くなるため、これ以上は必要が無いと判断し、副腎はホルモンを分泌しなくなります。このような状態が長く続くと副腎の機能がしだいに衰えていきます。
私たちの体は非常に怠けもので、本来の体の働きを、長期間外からのものに頼り続けると、だんだんと働かなくなっていくのです。
このような副腎の働きの低下は、アトピーの症状の悪化を招きます。そして悪化したら中々治らないということになるのです。
副腎の働きを強くする方法
ここまで説明してきたように、副腎はアトピーの改善にとって、とても重要な臓器です。副腎を酷使するとアトピーの症状を悪化させてしまうことになります。しかし、反対に副腎の機能を強化することでアトピーが改善しやすくなります。
副腎の機能を強化する方法をご紹介します。
副腎を強化する栄養素を摂る
副腎を強くするためには、副腎への負担を減らすと同時に、副腎の働きをサポートする栄養素を積極的に摂ることが必要です。
ここでは、副腎機能強化に有効な栄養素について説明します。
ビタミンC
副腎の機能を強化する栄養素の筆頭は「ビタミンC」です。
ビタミンCには副腎がホルモンを作ることを助ける働きがあります。
副腎はたんぱく質を元にホルモンを作り出しますが、それを手助けするものとしてビタミンCを消費します。ビタミンCは体の中で作ることができません。炎症を鎮めたり、血糖値を調整したりするためにコルチゾールなどのホルモンが作られれば、その手助けをするビタミンCも不足してしまうのです。
材料となる物質を増やすことで、ホルモンを作り、分泌する機能をサポートするという考え方です。
ビタミンCを摂るには野菜を摂ることが重要です。ビタミンCは加熱に弱いため、生で食べるか、サッと炒めたり、タジン鍋で軽く蒸したりという短時間の加熱調理で食べるのが良いでしょう。
また、「ビタミンCといえば果物」と思う方は多いです。確かに果物にはビタミンCが豊富ですが、果物に含まれている「果糖」は血糖値を上げてしまうため逆効果になります。特にジュースだと、製造過程で加熱処理されるためビタミンCは壊れてしまっているのです。
ビタミンCは天然のものと合成されたものとで、それほど違いが無いため、単純に量を増やすということならば、サプリメントで補給することもいいでしょう。
【ビタミンCを多く含む食品】
パプリカ・菜の花・ミニトマト・カボチャ・サツマイモ・モロヘイヤ・ブロッコリー・カリフラワー・赤キャベツ・玉露など
ビタミンB群
ビタミンCと並んで副腎強化に有効なものはビタミンB群です。
ビタミンBには、ビタミンB1(チアニン)、ビタミンB2、B3(ナイアシン)、B5(パントテン酸)、B6(ビリドキシン)、B12(コバラミン)、葉酸、ビオチンの8つがあり、単体ではなく、それぞれが補い合いながら働くため、ビタミンB「群」と言われています。そのため摂取するときも単体ではなく群として摂る必要があります。
中でも重要なのがビタミンB5の「パントテン酸」です。
私たちの体にはブドウ糖からエネルギーを作る仕組みあり、その仕組みに必要なのがパントテン酸です。副腎がホルモンを作る時には大量のエネルギーを消費するためパントテン酸が必要になります。パントテン酸の不足は副腎機能の低下を意味するのです。さらに、ビタミンB3、B6も前述のビタミンCと同様にホルモンの合成を助ける働きをしているため重要です。
ビタミンB群は野菜より、肉や魚に多いという特徴があります。
しかし、含有量が少ない食品もあるためサプリメントで補うことも必要な場合があります。
また、ビタミンB群の一部は腸内細菌によって作り出すことができるものもあります。そのため、腸内環境を良くすることを意識することも大切です。
【ビタミンB群が多く含まれている食品】
| ビタミンB5(パントテン酸) | 働き | ・ブドウ糖からエネルギーを作る
・ホルモンを作るのを助ける |
| 食品 | 牛肉・豚肉・鶏肉・鴨肉・鶏レバー・ アワビ・シシャモ・タラコ・ウナギ・サツマイモ・納豆・モロヘイヤ・アボカド・エリンギ卵黄・牛乳・ヨーグルト | |
| ビタミンB3(ナイアシン) | 働き | 副腎皮質ホルモンの材料になる |
| 食品 | カツオ・鰹節・ビンナガマグロ・鶏胸肉・牛サーロイン・ブリ・ハマチ・クジラ・サンマ・サワラ | |
| ビタミンB6 | 働き | コルチゾールを作るために必要 |
| 食品 | マグロ・カツオ・サンマ・カジキ・サバ・ブリ・サケ・牛肉・豚肉・鶏肉バナナ・ピスタチオ・モロヘイヤ・サツマイモ・カボチャ |
たんぱく質
たんぱく質はホルモンを作るための材料となります。
副腎皮質ホルモンはコレステロールを材料に合成されますが、そのコレステロールの原材料がたんぱく質なのです。
アトピーの方へのたんぱく質の摂り方には一つ注意点があります。それは「植物性たんぱく質」を摂ることです。
動物性のたんぱく質は消化が難しいため、分解が不十分な状態で吸収される場合があります。未消化のたんぱく質を吸収してしまうと、体がそれをアレルゲン(アレルギーの原因物質)として認識し、アトピーの症状が悪化してしまいます。
しかし、動物性たんぱく質でも、魚類ならば肉類に比べて、消化に負担がかからないためあまり神経質にならなくても大丈夫です。
また、たんぱく質を取る際には、同時にたんぱく質の消化を助けてくれる「消化酵素」を多く含むものを食べ合わせることが重要です。
例えば、生の野菜などには消化酵素が豊富に含まれています。焼き魚に大根おろしを添えたり、お刺身にわさびをつけて食べたりという食べ方がおすすめです。
【(植物性)たんぱく質を多く含む食品】
大豆・豆腐・玄米・海苔・ゴマ・シイタケ・キクラゲなど
亜鉛
亜鉛は上記3つの栄養素のように直接副腎に作用するものではありませんが、副腎に負担をかける要素を減らし、間接的にサポートする栄養素になります。
亜鉛は糖からエネルギーを作る助けをする「酵素」を作るのに必要な栄養素です。酵素とは体内の様々な物質同士が反応することを促進する仲介役となるものです。
亜鉛が不足すると糖からエネルギーを作る仕組み(糖代謝)がうまく働かなくなります。そのため血糖値の調整がうまくいかず、血糖値の乱高下を招き副腎に負担をかけることになります。
また、亜鉛は膵臓(すいぞう)がインスリンを分泌するのを調節する働きがあります。亜鉛が不足するとインスリンの分泌が悪くなったり、過剰に分泌されたりします。そのため、抗インスリンホルモンであるコルチゾールの分泌も乱れ副腎に負担をかけます。
亜鉛を摂ることによって、糖代謝やインスリンの分泌を整えることができ、結果として副腎への負担を減らすことができるのです。
亜鉛は牡蠣や蟹などの魚介類、肉類であれば牛のレバー、牛肉、豚肉などに多く含まれており、特に牡蠣の亜鉛含有量はズバ抜けています。季節物ではありますが、意識して食べるようにするといいでしょう。
【亜鉛を多く含む食品】
牡蠣・カニ・牛肉・羊肉・鶏レバー・ホタテ・サバ・サケ・アサリ・カマンベールチーズ・カシューナッツ・アーモンド・煮干し・スルメ
ここまで紹介してきたような栄養素を摂取し、副腎の機能を強化することでアトピーが改善しやすくなります。ぜひ意識して摂取するようにしてください。
副腎の働きを強化するツボ(反射区)を刺激する
私たちの体には、副腎の働きを促進するツボのようなものがあり、そこを刺激することで副腎の機能を強化することができます。
「リフレクソロジー(reflexology)」という言葉を聞いたことはないでしょうか。
リフレクソロジーとは「反射(reflex)」と「学問(ology)」を語源としたもので反射療法とも呼ばれます。
人の体には、体内の臓器と繋がった末梢神経が集中した「反射区」というツボのようなものがあります。末梢神経とは体の末端部分(手足など)に通っている神経のことで、それと反対に脳や脊髄など体の中心を通っている神経を中枢神経と呼びます。
この反射区を刺激することで、体内の臓器の働きを促進させて自然治癒力を上げる方法をリフレクソロジーと呼びます。
副腎の働きを促進する「反射区」は手の平と足の裏に存在します。
順番に説明していきます。
手の平の反射区
手の平の反射区は図で示したように、人差し指と中指の間から垂直に線を下ろし、親指の骨の付け根とぶつかる辺りの位置にあります。

足の裏の反射区
足の裏の反射区は、足の人差し指から垂直に線を下ろし、ちょうど土踏まずに入るあたりにあります。

この部分をボールペンの頭や、人指し指の第二関節の部分で押し込むように刺激します。正しく刺激すると他の部分を押した時と違ってズンと響くような痛みがあります。
少し痛みが強いくらいに押すのがいいです。押した部分が紫色に変色する場合がありますが問題ありません。
上記の反射区を刺激することで、副腎の働きを促進しアトピーによる炎症を鎮める手助けとなります。手の平の反射区はいつでも押すことができます。気が付いたら押すような癖をつけるといいでしょう。
ここまで説明してきたように、副腎はアトピーを克服するために極めて重要な働きをする器官です。偏った食事などを続けて、酷使してはいけません。
負担をかけることをやめ、反対に副腎の機能を強化することで、アトピーの症状は格段に改善されます。